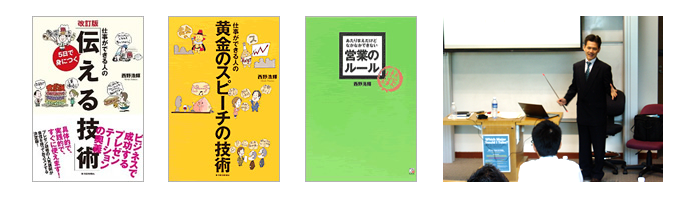以前Facebookで「考えが出てこないときは、手書きのマインドマップが効く」という投稿をしたところ、想定していた以上の反応をいただきました。
「やっぱり手書きは大事ですよね」 「手書きは、微妙なニュアンスもちょこちょこ書きやすい」 「手書きは、脳にとってまさに運動」そんなコメントが寄せられ、あらためて“手書きの力”を見直すきっかけにもなりました。
迷った時こそ、紙とペン
私自身、アイデアがまとまらない時や、何から手をつけていいか分からない時にこそ、紙に向かいます。
白紙の真ん中に〇を書き、そこから思いついた言葉を放射状にどんどんつなげていくマインドマップを「手書きで」描きます。
書き始めたときは散らかっていても、手を動かしているうちに不思議と脳がほぐれてくる。すると、ほぼ100%の確率でアイデアが浮かんだり、新しい観点に気づかされたり、良い言葉が降りてきたり。まさにひらめき脳が大活躍してくれて、無双状態になる。
この感覚は、タイピングではなかなか味わえません。
私のAIの基本的な使い方
とは言っても、私は「アナログ至上主義」ではありません。むしろ最近は、AIとりわけChatGPTをすごく重宝しています。
たとえば、「このアイデアをどういう構成で伝えればいい?」と壁打ちしたり、「この説明をもう少し相手目線で言い換えると?」と聞いてみたり。
Chat GPTは私にとって「ロジカルな相談相手」のような存在です。
目的がしっかり伝わると、意図を汲んで整理してくれ、さらに言語化までもサポートしてくれます。上手く使えば、思考が一気に整理・加速されていく実感があります。
手書きとAIのいいとこ
そんななかである日、ふと気づいたのです。「この『手書き』と『AI』の行ったり来たり」って、思考の『大谷翔平的二刀流』なんじゃないか?」と。
- 手書きは感性や直感、内省のピッチャー
- AIは整理や言語化のバッター
2つのツールを行き来することで思考が深まり、考えが結晶化される。
まさに「思考の二刀流」。
どちらかが正解という時代ではなく、「スイッチしながら使い分ける柔軟性」こそが、今の私たちに求められている力だと感じます。