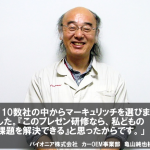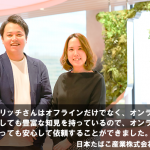| 導入前の課題 |
・エンゲージメント調査にて、管理職の「未来を語る力」不足が顕在化し、ビジョン共有が十分にできていなかった ・不確実な環境下で戦略実行を促す語りが弱く、社員の実行ドライブ醸成に課題があった ・率直な改善提案が行われにくく、フィードバックを通じて成長を促す組織文化の強化が求められていた |
|---|---|
| 研修内容 |
・執行役員・統括部長を中心とした約10名が参加し、ストーリーテリング研修を実施 ・目的を「ビジョンをわかりやすく魅力的に語る力の向上」とし、役職混在での演習と相互フィードバックを構成 ・フィードバックの観点を可視化したスキルチェックシートを配布し、受講後の自己評価も可能とした |
| 導入した結果や成果 |
・研修中に活発なフィードバックが行われ、上下間でも率直な指摘が生まれ始めた ・受講後アンケートで高スコアが得られるのみならず、「物事をストーリーで語る重要性」の認識が全社に広がった ・受講者がスキルチェックシートで継続的に自己評価を行う運用が開始された |
株式会社イトーキ様は、日本を代表するオフィス家具メーカーです。近年はミッションステートメントに「明日の『働く』を、デザインする。」を掲げ、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスを手がけるなど事業領域を拡大しています。 同社では2024年10月、エグゼクティブ層を対象にストーリーテリング研修を実施。研修を企画運営された人事本部人事統括部人事企画室長の仲本大輔様に、研修を実施した狙いや運営面での工夫点等についてお話を伺いました。
エグゼクティブ層の「語る力」が社員を動かす
イトーキ様では、このたび役員・管理職を対象にストーリーテリング研修を実施されました。まずは研修実施の狙いを教えてください。

仲本様 当社では毎年、エンゲージメント調査を行っています。その調査結果によれば、当社の管理職は「部下に寄り添いながら、彼らの仕事をサポートしていく」面では、毎年高いスコアを得ています。一方で「部下に対して、仕事の意味合いやビジョンを語る」という点については、苦手とする管理職が多い傾向が出ています。 調査結果から浮かび上がってきたのは、当社の管理職は「目先の対象・目標」に向かって一生懸命取り組むことが強みである一方で、「3年後や5年後の当社のありたい姿やあるべき姿」といった「長期的な未来を語る力」については、改善の余地がありました。これが本研修を実施することにした一番の理由です。
管理職の「未来を語る力」を高めることは、なぜ重要なのでしょう?
仲本様 不確実性が高まり、変化の激しい昨今においては、優れた戦略を考えることも大切ですが、それ以上に、今後はそれを実行するヒトを動かす力が重要だと考えています。
AIやテクノロジーの進化に伴い、戦略上での独自性を打ち出していくことは、次第に難しくなるでしょう。
そうなると戦略の優劣ではなく、立てた戦略を社員一人ひとりが強い思いを持って実行できるかどうかが、従来以上に事業の成否を分けることになります。これを実現するためには、リーダーが「この戦略を実行することによって、どんな未来が待っているか」を魅力的な言葉で語ることで、社員一人ひとりを惹きつけ、強力に動かしていける力を身につけることが必須となります。 もちろん、短期間でそのレベルにまで到達するのは困難です。ですから現実には、リーダーが「未来を語ろうとする意識を持つこと」や「以前よりもわかりやすく話せるようになる」だけでも、大きな前進だと考えており、本研修はその試金石になれば良いと考えておりました。
今回の研修の受講対象者は、どのように選ばれたのでしょうか?
仲本様 執行役員とそれに準ずる統括部長を受講対象のメインに据えました。「未来を語る力」を組織全体として高めていくためには、まずはエグゼクティブ層から変わっていく必要があると考えたからです。エグゼクティブ層が変われば、それがミドル層の管理職へと伝播し、「未来を語ること」が組織全体の文化になっていくことが期待できます。
研修を実施するにあたって、受講者により高い意識を持って参加してもらうために、工夫したことはありますか?
仲本様 強制ではなく、手上げ方式にしました。課題意識を持ち、変わりたいという意思のある人だけが受講するかたちにしました。自発的な学びでなければ、効果がないと考えたからです。もし受講希望者が一人もいなければ、研修の実施自体を見送るつもりでした。 実際には、受講対象者の約1.5割にあたる10人程度が手を挙げてくれました(ただし10名の中には一部部長職の社員も含まれます)。十分な参加人数とは言えませんが、それでも、意義のある一歩でした。エグゼクティブ層の一部ではありますが「未来を語る力」の重要性を認識し、その能力を身につけることができれば、彼らが持つポジションパワーによって、組織に与える影響力は非常に大きなものとなります。
「Moreを伝えることの重要性」を強調してくれた
研修会社にマーキュリッチを選ばれた理由を教えてください
仲本様 当初、複数の研修会社さんに問合せを行いました。
私たちが求めたのは、「エグゼクティブ層がビジョンをわかりやすく魅力的に語れるようになること」です。このスキルが身につけば、社員の心を掴み、彼らの行動を促していくことが可能になります。マーキュリッチさんが示してくださったストーリーテリング研修のプログラムは、まさに私たちの課題感を解決してくれる内容であると判断したため、お願いすることにしました。 ちなみに私が研修会社に依頼をするときには、最初から「○○研修を実施してほしい」といった具体的な研修名は挙げないようにしています。「○○の課題を解決したいので提案してほしい」というように、当社が直面している課題や研修を実施する目的を話すようにしています。私たちが実現したいのは課題の解決であり、研修はそのための手段です。目的を明確に示した上で、手段については研修のプロフェッショナルである研修会社の提案を最大限に活かすという姿勢を大切にしています。
研修内容について、事前にマーキュリッチに相談したことや依頼したことはありましたか?
仲本様 当社は「人に優しい社風」と言いますか、相手に何か伝えるときにも、ポジティブなフィードバックはできるのですが、改善点を指摘するのが苦手という課題があります。これはエグゼクティブ層に限らず、あらゆる階層の社員にいえることです。
そのため、以前ほかの研修を実施した際に起きたのが、受講者同士で「Good&More」を言い合う場面で、Goodばかりが出てきてMoreが出てこないことでした。これでは本当の意味で気づきを得られる研修にはなりません。特に今回の研修の場合、役職の異なる受講者が混在するため、上下関係を意識して部下から上司に対して率直なフィードバックが行われにくくなるのではという心配もありました。
その点を今回講師を務めたマーキュリッチの西野さんにあらかじめお伝えしたところ、西野さんは当日の研修の中で、「GoodだけではなくMoreを伝えることの重要性」を折に触れて受講者に語りかけてくださいました。そうしたこともあり、本番では活発なフィードバックが交わされていました。
講師に求める3つの要素をすべて満たしていた
当日の研修について、印象に残っていることを教えてください

仲本様 エグゼクティブ層を対象とした研修の場合、講師の知見や経験値の高さがとりわけ重要になってくると思います。エグゼクティブ層が組織の中で求められている役割や直面している課題を講師が掴んでいないと、受講者に対して適切な問いかけやフィードバックをすることはできません。その点、西野さんは豊富な経験に裏打ちされた表現の引き出しを数多く持っており、受講者の問題意識のポイントを掴んだ事例やヒントを的確なタイミングで提供していました。 私は講師の方に対して、「受講者を研修に巻き込めているか」「受講者に対して効果的な問いかけができているか」「受講者からの問いに対して明確な回答ができているか」の3つが重要になると考えていますが、西野さんがその3つの要素をいずれも満たしていました。
受講者の反応はいかがでしたか?
仲本様 みなさん、とても真摯な姿勢で受講していました。
実は当社では、エグゼクティブ層を対象とした研修は今回が初めてでした。部長職以上については、それぞれの役割に応じて課題や強化すべきポイントが異なるため、一律の研修よりも個別の自己研鑽に委ねるというのが基本方針でした。しかし学びたいという意欲は誰もが持っているものですし、変わろうとしている人を支援することは階層に関わらず重要だと考えるようになりました。そこでエグゼクティブ層向けの研修に踏み切ったわけです。
とはいえ初めての試みでしたので、最初は正直なところ、どこまで受講者が真剣に取り組んでくれるか不安もありました。しかし結果は成功でした。これは公募制にしたことも大きかったと思います。自ら手を挙げて参加された方々なので学びへの意欲も高く、西野さんのファシリテーション力の高さも相まって、研修全体を通して非常に積極的に参加されていました。
受講後に実施したアンケート結果でも、非常に高いスコアが得られました。「物事をストーリーで語ることの重要性を改めて認識した」という感想や、「統括部長や役員クラスになると、改善点を注意してくれる人が周りにいなくなるので、フィードバックをもらえたこと自体に価値を感じた」という感想もありました。
研修の効果についてはどのように評価されていますか?
仲本様 一日の研修で、エグゼクティブ層の「未来を語る力」が一気に高まるようなことは、最初から期待していませんでした。大切なのは、受講者一人ひとりが「長期的なビジョンを持ってストーリーで語ることの重要性」を認識したうえで、自分にはそれができているかを内省し、自身を変えていこうとする姿勢を受講後も保ち続けることです。
どこまでいっても、研修はそのきっかけを作るのが役割です。 マーキュリッチさんには、受講者が自身のストーリーテリング力についてのスキルレベルを把握するための「スキルチェックシート」を準備いただき、研修時に受講者に配布しました。 受講者がこの「スキルチェックシート」に受講後も定期的に立ち返り、自己評価を行うことで、当社のエグゼクティブ層の「未来を語る力」は、今後確実に伸びていくことが期待できます。
本日はありがとうございました。貴重なお話をうかがうことができました。

※株式会社イトーキ ホームページ
※取材日時 2025年4月
※当ホームページに掲載されている文章、画像等の無断転載はご遠慮下さい