
組織を取り巻く文書作成の現状
組織において、文書作成は単なる業務の一部ではなく、コミュニケーションの中心的な手段となっています。特にリモートワークが発達したなかで、チャット・メールの頻度・重要性が高まっています。加えて、以前と同様に報告書・議事録なども多数存在します。
こうした情報が適切に「文字情報として蓄積」されていくことは大きな意味があります。蓄積した情報をAIと連携させることで、AIが最適な行動をとりやすくなるからです。
たとえば商談記録がしっかりと書かれていれば、それを与えたAIは最適な提案書を出力しやすくなるなどです。
情報伝達の非効率性
そうして文書作成の重要性がたかまり、文章を書く頻度があがるほど、我々は文章を書くことに時間を割かざるを得なくなっています。我々が研修を実施するなかでも受講者の悩みとしてもっとも多いのが「時間がかかる」です。
加えて、その文章が読みにくいものだとしたら読み手にも負担がかかります。それどころか、誤解を生むような文章になっていたとしたら、読み手の判断や意思決定に間違いを起こさせてしまいかねません。
生産性を阻害する文書作成の課題
これまでも起こっていたこうした問題が、これから先のAI時代はより一層起こりやすくなっているということです。
しかし、組織のライティング教育は十分とはいえず、個々人の能力に任せられているのが現状です。体系的な文書作成スキルの育成や、組織全体での知識共有が不足しているため、属人的なスキルに依存する状況が続いているのです。
今後、加速していくAIを活用しての文書作成
少し未来の話をしますと、AIの進化によりキーボード入力による文書作成は徐々に減少していくでしょう。これは生産性向上の可能性を秘めていますが、同時に新たな課題も生まれています。
AIによる文書作成の落とし穴
- 放置すると文章が冗長になりがち
- 意図から外れた内容が生成されるリスク
- 単純な「丸投げ」では質の低い文書になる
AIを適切に制御するために必要なスキル
- 自身の考えを明確に言語化する能力
- 事前にAIに渡す情報の設計(コンテキストエンジニアリング)
- AIへの指示のしかた(プロンプトエンジニアリング)
- 継続的な文書の微調整と最適化(評価とフィードバック)
どうせ今後につながる資料作成能力をつけるのであれば、こうしたAIをうまく活用し、落とし穴につまずくことなく生産性を高めるスキルを身に着けたいと思うのではないでしょうか。
課題解決への革新的アプローチ
2段階の学習設計
弊社のプログラムでは、こうした状況下において2段階の構成をとっています。
第1段階:基礎的な文書作成能力の習得
そもそも本人がうまい文章を書けることなしに、AIに良い文章を書かせることはできません。なぜならば、AIが出した文章を評価することができないからです。だからこそ、まずは基礎的な文書作成能力を総合的に身につけることを目指します。
文書作成能力を構成する3つの要素
- コンテンツ:内容 – 端的さ・網羅性・具体性
- ストラクチャー:構成 – 情報の構造化・書く順番構成
- デリバリー:見せ方 – 文章術・図解・レイアウト
これら3つの能力をさらに細分化し、個別の要素に落とし込んで習得していきます。
第2段階:AIを活用した生産性向上
そしてそのプロセスの中で、AIをどのように活用すれば良いかという内容を随所に絡めながら進めていきます。
– AIをどのように活用すれば、生産性を高められるのか
– AIをどのように活用すれば、自分が悩む時間を短くすることができるのか
学習による2つの成果
このアプローチにより、以下の状況を実現できます:
1. AIなしでも対応可能 – 仮にAIを使わなかったとしても、自分一人で適切な文章を作成することができます
2. AIの活用で生産性が加速 – もしもAIを使用する許可が得られている場合、その生産性をさらに加速させることができます
本研修で成果をだすために我々が心掛けていること
学習コンセプト:フォーカスする
この研修で私たちが最も大切にしているのは、「フォーカスする」という姿勢です。
研修の中では多くの知識やスキルに触れます。たとえば今回のプログラムでは、「コンテンツ」「ストラクチャー」「デリバリー」という3つの要素を軸に進めていきます。この要素はさらに細かく8つの要素に分類されていきます。
さらにそれぞれを掘り下げれば、理解すべきことは膨大です。すべてを完璧に身につけようとすれば、かえって本質を見失ってしまうことにもなりかねません。
前提にあるのが「人は多くを持ち続けられない」
だからこそ私たちは「すべてを抱え込むのではなく、確実に掴むべきものにフォーカスする」ことを重視しています。多くのボールを空中に投げ続けるよりも、現場に戻っても手放さない1つか2つのボールをしっかり掴み続けること。
それこそが、現実的で持続可能な成長の形です。なぜならば業務に戻れば新たな情報が与えられ、自分で大事だと思ったことすら記憶の奥底に追いやられてしまうからです。だからフォーカスなのです。
そしてこの「フォーカス」を支え、継続を可能にする存在がAIです。AIの使い方をワークフローに落とし込むことで「自分で決めた数少ないことをきちんとやり切る」が可能となってきます。
AI×文書作成研修のゴール
第1のゴール「読み手にとってわかりやすく、構造的に整理されたドキュメントを書く力」
情報を整理し、論理的で読みやすい形にまとめる力を磨くとともに、それを短時間で仕上げる実践的なスキルを身につけていきます。AIを使う・使わないにかかわらず、まず自分の手でそれを実現できること。それが最初の到達点です。
第2のゴール「AIの力でドキュメント作成力を加速させる」
今後、私たちが「自分でキーボードを打って文章を書く」機会は、確実に減っていきます。だからこそ、AIをどう使うかが生産性と成果の質を大きく左右します。
単にスピードを上げるためのAIではなく、「ドキュメントの質を下げないためのAI活用」を多面的に学ぶ。人の思考力とAIの補助力をどう組み合わせれば、より正確で、より伝わるアウトプットを生み出せるのか――その設計思想を体得することです。
AI×文章作成研修の内容
イントロダクション
- ライティングの重要性と活用場面
- 文章ライティングスキルの自己チェック
AI×文章作成におけるマインドセット
- どのAIツールでもよいから日常的に触ろう
- 自分の知能を低下させないAIの使い方をしよう
0章:とりあえずAIをさわってみる
- 基本的な生成AIの使い方
- 日常の使い方を振り返る
- AI活用の大前提:音声入力をマスターする
- 【演習】音声入力演習
キックオフ演習:わかりにくい文章を書き換える
- わかりにくいメール文面を書き換える
- 自分の書き換え後文章を振り返る
コンテンツ~話の内容~
端的に書く力
- 上司層に聞いた「部下の文章、ここが困る」
- 端的に書くべき3シーン
- 【演習】シンプルメッセージ演習
- 【演習】AIにシンプルメッセージを作らせる
網羅的に書く力
- こちらの目的達成に必要なことを書く
- 【演習】目的思考レッスン
- 読み手の判断・理解に必要なことを書く
- 【演習】読み手の興味と理解を考える(self/AI)
- 【演習】依頼文を目的思考・読み手思考から考える(self/AI)
具体的に書く
- 絵が浮かぶように書くことの重要性
- 【演習】具体的に表現するレッスン(self/AI)
ストラクチャー~文章の構造化~
頭のなかにあることを構造化する
- 図解:グルーピング&関係性をつなぐ
- 【演習】構造がみえにくい文章を再整理する(self/AI)
構造化した情報を文章構成に落とし込む
- 報告型文書は「結論-前提-内容-意見」
- 説得型文書は「結論-課題-課題の分析-解決方針-具体策」
- 構造化をカスタムAIで自動化する
- 【演習】カスタムAI作成演習
デリバリー~見せ方~
図解
- 図解はなぜドキュメントで必要か
- 図解作成をAIの活用で省力化する
- 【演習】AI図解作成
レイアウト
- 文章内の強弱を見えやすくするルール
文章術
- 1文60文字以内を実現する3つの方法
- 【演習】60文字実現演習
総合演習
- 【演習】特定の場面設定のもと、AIを使いながら文章をつくる
- 【演習】アウトプットとプロセスへのフィードバック
講師紹介
 マーキュリッチ代表取締役
マーキュリッチ代表取締役西野浩輝
「人は変われる!」をモットーに年間150日の企業研修をおこなう教育のプロフェッショナル。トップセールス・経営者・外資系勤務など、これまでの自身の経験を活かして、グローバルに活躍できるプレゼンター人材の輩出に取り組んでいる。
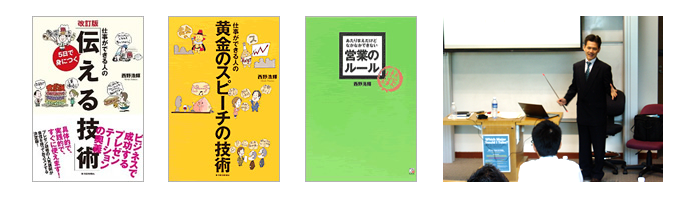
 マーキュリッチ取締役
マーキュリッチ取締役野村尚義
15年間で20,000人のプレゼンを指導してきたプレゼン・アドバイザー。いつも選ばれ続けるトップ1%のプレゼンの分析から、成果直結型のメソッド"ダイヤモンド・プレゼンテーション戦略"を体系化し、それを用いた指導をおこなっている。

