
「伝わる」から「動かす」へ──プレゼンの成果を高める
本研修では、従来の「分かりやすく伝える」から一歩進み、聞き手の心を動かして具体的な行動を引き出すスキルを身につけます。営業提案、社内プレゼン、チームマネジメントなど、あらゆる場面で使える実践的な技術です。
こんな課題をお持ちではありませんか?
プレゼンテーションにおいて、どれだけ論理的に説明しても相手の心に響かず行動につながらない。貴社でも、同じような課題を感じることはありませんか?
これらの課題に共通するのは、プレゼンで「分かりました」と言われたのに、その後何のアクションも起きないという状況です。
顧客や取引先への提案で
念入りに準備した資料とロジックで臨んでも、相手の心を動かせず案件が流れてしまう。
- 「検討させていただきます」と言われ、その後連絡が途絶える
- 競合他社が選ばれ、「決め手は何だったのか」がわからない
- 技術的な質問は多く出るが、導入への前向きな話に発展しない
社内での新しい施策のプレゼンで
理屈では納得しているはずなのに、実際の行動が伴わない。
- 「必要性は理解できるけど、気が進まない」という反応が多い
- 施策の目的や意義が”自分ごと”として受け取られていない
- 取り組みが空回りし、進まない要因を”納得感の不足”だと感じる
チームやメンバーに向けたプレゼンで
方針や目標を伝えても、メンバーの動きが鈍い。
- 現場での自発的な行動が見られない
- 部下やメンバーが共感せず、内発的な動機づけが生まれにくい
- 意図や背景は伝わっても、”信頼感”や”共通理解”が築けていない
なぜ、これらの課題が起こるのか? ── 「感情への配慮不足」という問題
上記のようなプレゼンの成果が出にくい状況は、聞き手の感情や心理的なプロセスに対する配慮が不足していることが原因の一つです。つまり、伝える側が「聞き手が今どのような気持ちで話を受け取っているのか」「何に興味を持ち、何に心を動かされるのか」を十分に想像しきれていない状態です。
こうした“感情の配慮不足”があると、聞き手には以下のような状態が生じます。
- 話し手の説明に置いてけぼりにされる
- 情報は頭では理解できても、自分に関係する話だと感じにくい
- 「だから何をすればいいのか」が曖昧なまま終わる
- 内容が心に響かず、行動につながらない
このように、聞き手が話の内容を「自分ごと」として捉えられなければ、どれだけ論理的な説明がなされていても行動にはつながりにくいのです。
行動につながる心理的メカニズムとは?
人が行動を起こすには、納得や共感など、内面の動機づけが必要です。心理学的には、行動の原動力となる「動機」は、主に以下の2種類に分類されます。
| 比較軸 | 外発的動機(例:上司の指示) | 内発的動機(例:自分の中の納得) |
|---|---|---|
| 行動のきっかけ | 義務感、評価、報酬など | 納得感、価値観の一致、意味の理解など |
| 行動の温度感 | 淡々と取り組む | 前向きに取り組む |
| 継続性・自走性 | 環境に依存しやすい | 意思が伴うため継続しやすい |
| 創意工夫 | 限られた範囲で行動する | よりよくしようと自ら改善や提案を行う |
感情に配慮しないプレゼンは多くの場合、聞き手の外発的動機にしか訴えかけられません。 たとえば「上司に言われたから」「他部門の手前、やらざるを得ない」といった動機では、自発的な行動や継続的な取り組みにはつながりにくいのです。
一方で感情に適切に働きかけ、「これは自分にとって意味がある」「納得できる」と感じさせることができれば、内発的動機を引き出すことができます。
共感とは──内発的動機を引き出す鍵
内発的動機を引き出すうえで欠かせないのが「共感」です。
共感とは相手の立場や感情を理解しようと努め、「この人は自分のことをわかってくれている」と感じられるような状態を指します。 この共感があることで相手との間に信頼関係が生まれ、メッセージを「自分ごと」として受け止めやすくなります。
プレゼンテーションにおいては話し手が共感を意識して伝えることで、聞き手は「自分のことを理解してくれている」と感じやすくなり、内発的な動機が刺激され行動へとつながっていきます。
共感は偶然に任せるものではなく、意図して生み出すことが可能です。
共感プレゼンテーション研修では
本研修ではこの共感を意図的に生み出すための構成や伝え方の技術を習得していただきます。理論だけでなく、実際のプレゼンシーンで使える実践的なスキルを身につけることが研修の目的です。
本研修で期待できる効果
本研修を通じて共感プレゼンのスキルを身につけることで、社内外の様々な場面で具体的な効果を実感していただけます。
1)プレゼンが「伝わる」から「動かす」に変わる
共感によって聞き手の”理解”を”行動”につなげる力が育ちます。情報やロジックだけでは届きにくい”心の部分”に焦点を当てることで、営業提案や社内プレゼン、マネジメントの現場でプレゼンの成果を一段上のレベルに引き上げることが可能になります。
2)自発的な行動を促す力が身につく
外発的動機ではなく内発的動機に働きかける技術が身につきます。聞き手自身が「やりたい」「取り組みたい」と思える状態を作り出すことで、継続性があり、創意工夫を伴った質の高い行動を引き出すことが可能になります。
3)共感を再現性のある技術として習得
共感を「意識」ではなく「技術」として習得できます。聞き手の状況や感情に寄り添いながらメッセージを構築する視点と構成法を、フレームや事例を用いて実践的に学びます。その結果、社内外の関係性を築く力、巻き込む力が自然と育まれます。
4)学んだ内容をそのまま実務に応用可能
研修翌日から現場で実践できる状態を目指します。共感を「感覚」ではなく「構造」で捉えるアプローチにより、研修後も現場で使い続けられる再現性の高いスキルとして身につきます。「I–You–We」フレームなどの枠組みに、自身のプレゼンテーマを当てはめながら演習を行うことで、学びをそのまま実務へ応用できる状態を目指します。
研修の理論的基盤
感情に焦点を当てた体系的アプローチ
古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、説得には「エトス(信頼)」「パトス(感情)」「ロゴス(論理)」という三つの要素が必要だと説きました。本研修では、この三要素のうち「パトス=感情」に焦点を当て、聞き手の心を動かし、行動へと導くための考え方と実践的な手法を体系的に学びます。
共感を生み出すための6つの本質的要素
本研修では以下の6つの本質的要素を理論的基盤として、体系的なアプローチを採用しています。
共感を構成する6つの本質的要素は、プレゼンテーションにおいて聞き手の感情を動かすための”感情的インフラ”とも言えます。これらの要素を理解し、自らのメッセージ設計に取り入れることで、共感は”偶然”ではなく”再現可能”なものになります。

- 相手の立場に立った視点
- 感情に訴える具体的なエピソード
- 共通の価値観や目標の提示
- 聞き手の課題への深い理解
- 自分自身の体験や想いの開示
- 未来への共通のビジョン
これらの要素を段階的に学び、実際のプレゼンテーションに組み込む技術を習得していきます。
プログラム内容
イントロダクション
- 共感プレゼンとは?
- なぜ今、「共感」なのか?
- 共感できるプレゼン、できないプレゼンの違い
- 【演習】自分自身の共感プレゼンスキルを分析、把握する
- 【演習】当研修のゴールを設定する
共感コミュニケーションのメカニズムの理解を深める
- 共感をもたらす6つの要素とは?
- 相手の立場に立った視点
- 感情に訴える具体的なエピソード
- 共通の価値観や目標の提示
- 聞き手の課題への深い理解
- 自分自身の体験や想いの開示
- 未来への共通のビジョン
- プレゼンへどう反映するか?
- ロジカルと共感をどう両立するか?
共感を起こすステップとは?
以下の要素を段階を踏んで実現する
- 感情移入:「頑張っているな」「応援したいな」
- 自分への影響:「これは自分に関係があるぞ」
- 共に行動したいという気持ち:「一緒にやりたい!」
共感プレゼンのための基本的フレームワーク
- 「I・You・We」の3要素の活用
- 【演習】自身のプレゼンを「I・You・We」フレームワークに当てはめる
共感プレゼンを作るための第一歩
聞き手イメージング
- 聞き手のBeforeの気持ちを言葉にする
- あなたのプレゼンを聞いた直後に持たせたい「感情リスト」
- 「BeforeーAfter」のGAPを埋めるコツ
- 【演習】聞き手の心の声の「BeforeーAfter」を考える
- 【演習】GAPを埋めるための内容を考える
共感、共鳴を起こすためのメインメッセージ
- メインメッセージの重要性
- メインメッセージの作り方
- 作成のための情報ソース
- 作成のための4つのテクニック(リピート法、ギャップ、「NotA・ButB」構文、比喩)
- 【演習】自身のメインメッセージを明確化・先鋭化する
聞き手の感情を動かし、共感を作るフォーマット
- サンドイッチフォーマット
- 聞き手の感情デザイン
- 【演習】自身のプレゼンにおける「感情デザイン」を考える
- サンドイッチフォーマットと「I・You・We」フレームの関係性
イントロでのポイント
- 自分・自部署の課題描写で共感を誘う
- 自分自身の情熱を伝える
- 「相手の課題⇒共感⇒あおり⇒深掘り」のプロセス
- 共通の仮想敵を描く
ボディ(本論)でのポイント
- 解決コンセプトで共感を作るコツ
- 無味乾燥にならないアクションへ繋げるには?
エンディングで一体感を作る
- 対面プレゼンから「側面」プレゼンへ
- 相手の目線に降りていく
- 共通の未来を描くコツ
- 【演習】サンドイッチフォーマットに当てはめる、or 修正する
共感創出の応用テクニック
- 問いかけ
- 感情言葉の活用
- 「あるある」列挙法
- 失敗事例の先出し
- 感情を想起する比喩
- マイクロストーリー
共感を呼び起こす話し方
- 声色の使い分け
- 「間」を効果的に作る
- 表情で、心の動きを感じさせる
- 一体感を作るためのボディムーブメント
- 目線で聞き手との感情の繋がりを作る
- 【演習】語るスキルのトレーニング
総括プレゼン・シミュレーション
- 1人1人からプレゼンテーション
- 講師からのフィードバック
- 受講者相互フィードバック
- ビデオプレイバック分析
感情に届くプレゼンが、行動を生み出す。
「伝えているのに、動かない」 「理解はされても、共感されていない気がする」
そんな現場の声に、何度となく向き合ってきました。
マーキュリッチの共感プレゼンテーション研修は、プレゼンの”感情面”に焦点を当て、聞き手の心に届き、行動を引き出すコミュニケーションを支援します。
「共感の力を組織に取り入れたい」 「情報だけでなく、”想い”も伝えられる人材を育てたい」
そうお考えの人事・育成ご担当者様、まずはお気軽にご相談ください。 貴社の現場課題にあわせた導入方法をご提案いたします。
講師紹介
 マーキュリッチ代表取締役
マーキュリッチ代表取締役西野浩輝
「人は変われる!」をモットーに年間150日の企業研修をおこなう教育のプロフェッショナル。トップセールス・経営者・外資系勤務など、これまでの自身の経験を活かして、グローバルに活躍できるプレゼンター人材の輩出に取り組んでいる。
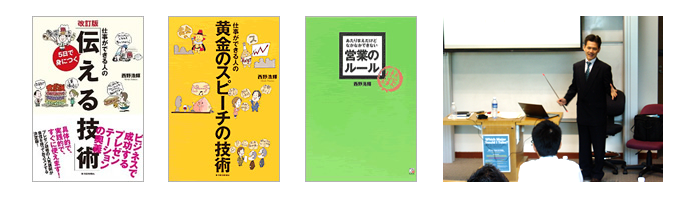
 マーキュリッチ取締役
マーキュリッチ取締役野村尚義
15年間で20,000人のプレゼンを指導してきたプレゼン・アドバイザー。いつも選ばれ続けるトップ1%のプレゼンの分析から、成果直結型のメソッド"ダイヤモンド・プレゼンテーション戦略"を体系化し、それを用いた指導をおこなっている。

